トコトンやさしい鉄の本 (B&Tブックス 今日からモノ知りシリーズ)解説
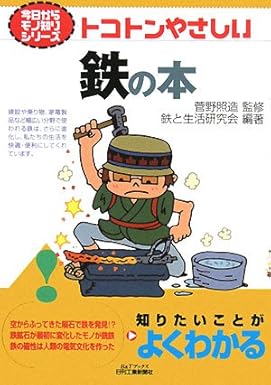
トコトンやさしい鉄の本 (B&Tブックス 今日からモノ知りシリーズ)口コミ
高炉の構造なども図もあり、また内容がまとまっており、とても勉強になりました。
参考になった部分は下記です。
鉄鉱石と石灰石を一緒に焼き固め、石炭(コークス)を高炉の中に入れる。鉄鉱石とコークスを交互に積み、下から2200~2500°で熱する。
鉄鉱石の酸素が、コースの燃焼で発生したCOと反応して、鉄分が炉の底部に沈殿する。それを銑鉄と呼ぶ。銑鉄は炭素を含んでおり、固くもろく叩くと割れる。
銑鉄は転炉に運ばれ、石灰を加えられる。石灰は鉄鉱石中の二酸化ケイ素や酸化アルミニウム酸化物、硫黄などと化合して、「スラブ」と呼ばれるカスを作る。ここでできた鉄を「鋼」と呼ぶ。
電炉メーカーは、銑鉄を作る製銑工程を持たずに鉄くずを主原料として、電炉で製鋼する。
特殊鋼メーカーは、特殊鋼をより上質なものにするための精錬や目的に応じた形に加工するための圧延、鋳型に流し込んで形を作る鋳造を専業とする。
直接還元プラント鉄では天然ガスを使用して鉄鉱石を還元するプラントで、高炉のような大規模の設備は不要で、コークスも不要となる。天然ガスを産出する途上国でミニミルとして建設されてきた。
熱を加えると鉄の原子の間は長くなりお互いに引き合う力が弱くなり、鉄が溶け始める。(1000度くらい)。長くなった原子の間に炭素が張り込み、還元が進む、そうして、銑鉄、鋼が出来上がる。
焼き入れ(急冷)を行うとより硬い鋼ができ、焼き戻し(150度くらいで再加熱)を行うと延性や靭性(しなやかさ)が強くなる。
オーステナイトを急冷し、マルテンサイトになる。マルテンサイトのまま使用することは稀で、焼き戻しを行うのが普通。
ステンレスは、表面がサビの薄い酸化被膜で覆われており、サビの進行を抑えている。
鉄鉱石から鋼を作るまでの工程や、焼入れなどの加工、原子の仕組みまで書かれて、勉強になりました。
本自体の内容は何も問題ないが、購入した商品がものすごくカビ臭い。
しっかり管理してください。
I’m not a Japanese but I can read Japanese a little
This book is very nice and easy to understand
Thanks to this book
近年、中国での鉄の生産と消費によって、世界の鉄鉱石の需要が急増しているとニュースに接したこともあり、そもそも「鉄」とは何か、というレベルから関心を持って本書にたどりつきました。
『トコトンやさしい鉄の本』というタイトル通り、実に平易に魅力的に知らなかった世界、もしくは知っているつもりだった知識の整理に役立ちました。文系人間にとってはこのような初心者向けの本はありがたいと思いましたね。
章立ては、「鉄はどこから来たのだろう」「鉄はどうやって作られるのだろう」「世界の最先端をいく日本の製鉄メーカー」「鉄の特徴といろいろな加工法」「鉄の天敵・サビとの関係」「いろいろな鉄とその応用」と括られています。
各項目は、見開きの2頁で完結しており、右の頁にページに解説、左の頁に図表やイラストが掲載されています。基本的な鉄の性質やその組成、性能、など中学校の理科の知識があれば楽しく読める内容でしたが、歴史好きの者にとっても興味深い記述が並んでいました。
項目だけを取り出して列挙しますと、最強の鉄文化の国ヒッタイト、中国の発展を止めた鉄の力、鉄をめぐるヨーロッパと中国の違い、近代の日本史をつくった鉄、鉄は日本近代化の象徴となった、一代限りの「たたら吹き」で和鋼を作る、鉄と弁慶の泣きどころ、戦争が鋼の溶接技術を進歩させた、ブリキが日本を救った?!、鉄船はコンパスを狂わせた?、鉄骨構造に多大な貢献をしたエッフェル搭、鉄銭の悪評が世界最初の紙幣発行につながった、鉄を鍛えた日本刀は神秘の力をもつ、鍔(つば)もまた鉄の芸術、などです。
初心者を対象に難しい内容を分かりやすく具体的に書く能力と言うのは実に大変な作業だったと思いますが、このような良書があれば、理系離れも少なくなるのではと思いました。
現代は、未だに鉄器時代だと思います。
鉄は国家なりという言葉があります。
自動車にしても、鉄道にしても、まだまだ鉄が主流です。
そんな現代の技術の基本を理解するのによい1冊です。
