モビリティX シリコンバレーで見えた2030年の自動車産業 DX、SXの誤解と本質解説
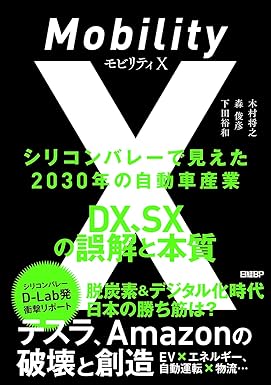
 CASEの各要素を掛け合わせながら、ロボタクシー事業を推進するGMとGoogle(本書より)
CASEの各要素を掛け合わせながら、ロボタクシー事業を推進するGMとGoogle(本書より)
モビリティX シリコンバレーで見えた2030年の自動車産業 DX、SXの誤解と本質口コミ
日本では、EVのことだけや、自動運転だけのことをバラバラに捉えてしまっているけど、
実はアメリカではテスラなどエネルギー産業も巻き込んでロボットタクシー時代を見据えて着々と社会実装されている話は、非常に参考になった。
またテスラだけではなく、既存自動車会社GMの動きも対比されていて現状のモビリティ産業の理解が進んだ。
あと自動車産業だけではなくアマゾンのモノの移動を軸にしたモビリティ戦略は、
ついに自動車産業にもアマゾンが来るのかと脅威を感じ、学びも多かった。
全体通してアメリカのモビリティ産業全体のトレンドが把握でき、さらに今後のモビリティ産業を考えていく上で非常に参考になった。日本産業が頑張ってほしいと思える良書だと思った。
この本は、100年に一度の大変革期の今、その一つの中心であるシリコンバレーで、何が起きているかを解りやすく伝えてくれる一冊であり、自動車業界人必読の一冊と感じた。
コンセプトだけでなく、具体的な事例がかなり紹介されていたのが良かった
Amazonのお勧め欄に幾度か表示されたので、よく内容を確認しないまま購入
出版日が2022年12月、著書の中ではモビリティの潮流を「シリコンバレー」目線で解説し、日本企業への警鐘と提言を目的としていると見受けられる。
本書ではテスラがEVの覇者とあるが、茲許の中国メーカーの勃興はシリコンバレー流でも予測できなかった様子であることを鑑みると、業界地図の変動スピードがいかに速いかを感じることができる。
本書の大筋であるモビリティ産業そのもののトレンドは、2024年現在も変わっていないと思われるが、シリコンバレーが最先端である保証はどこにもないと感じさせる一冊。
モビリティ産業と異業種の融合については今まであまり考えたことが無かったが、体験をリッチにする上でも、ビジネスモデルを強化する意味でも異業種融合が重要であるというのは新たな視点であった。従来のモビリティ産業のプレーヤーより、書籍で扱われているGoogle, Amazonなどの方が顧客に関するデータや顧客体験をリッチにするコンテンツ、サービスを持っており、より豊かな顧客体験を創れる可能性があると感じた。Teslaがエネルギー産業という異業種を抑えていることで他のプレーヤーよりビジネスを優位に展開できる可能性がある点もよく理解できた。モビリティ産業のみならず、新規事業を考えている人にもおススメできる。
Must read for all Japanese Businesses looking at next generation mobility business
モビリティの進化について分析されていて、興味深い洞察を提供している。自動運転技術の普及に伴い変化する体験の重要性、所有から利用への変化やロボタクシー誕生に伴う新たな価値観とそこに生まれる可能性を実感した。また、モビリティに限らず、テスラのエネルギー産業への展望とその視野の広さに驚かされる。日本にいると部分的にもしくは恣意的に情報が得られるのみで、俯瞰的にGAFAMなどの視野や展望を察する事が困難であり、実際に私自身も、断片的な情報で誤認していたことがわかった。日頃はエネルギー産業とつながりが強く、理解していたつもりであったが、石油メジャーで電力大手の新しいビジネスモデルの方向性もあらためて彼らの動機や経緯も含めて整理して理解することが出来た。Amazonの例からも、物流の強みから、入口と出口をうまく抑える方法など非常に興味深い。
最後に述べられている日本の戦い方は、総論であり若干抽象的な印象だが、自身の考えや企業形態に合わせて考えるだけの気付きは、十分に得ることができる。一読をお勧めする
配送の問題だと思うのですが袋もビリビリ、中身の方も傷だらけです。
非常に悲しかったです。
