知られざる鉄の科学 人類とともに時代を創った鉄のすべてを解き明かす (サイエンス・アイ新書)解説
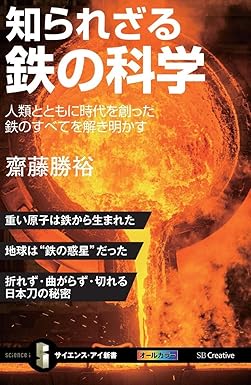
知られざる鉄の科学 人類とともに時代を創った鉄のすべてを解き明かす (サイエンス・アイ新書)口コミ
小さい子供が『空はなぜ青いのか?』はよく聞く質問である。
しかし、金属は何故ピカビカ光って見えるのか?を質問する小さい子は少ない。
この本を読めばそれが分かる。
それは金属表面に集まっている自由電子が、紫外線より周波数が高い電磁波を吸収して、可視光線を反射するので可視光線が強調されて見えるからなのである。
鉄というのは非常に歴史が古く、鉄の歴史は人類の歴史の大きな一部とも言える。
天然に存在する鉄は酸化鉄であるのはよく知られているが、鉄(2価イオン鉄)を食料にして生きているバクテリアがいる事に関して本書に記載があるのは驚きである。
このバクテリアは2価イオン鉄を食べて3価イオン鉄を排泄するのだからいわば電子を取り込んで生きている訳でまるで充電池の様な振る舞いをしている訳だ。
また、鉄もそうだが金属一般(半導体もそうである)にそれがナノクラスタサイズになると独特の性質(蛍光性やプラズモン共鳴)を示す。
例えて言えば、人間も集団でいる場合と少人数でいるのとは振る舞いが違う様に金属一般にもあるのは非常に面白い。
興味がある方は、『量子ドットの生命科学領域への応用』(シーエムシー出版)を読まれる事をお勧めする。
但し、内容は本書よりかなり高度である。
あと、鉄の話で欠かせないのは日本刀に関する話だ。
日本刀は少し曲率(反り)がついているが、これは人間的な意図でそうなっている訳ではなく刃は硬く心金(内部: 刃の反対側)は粘りを与える為の加工(焼き入れ)の過程でその様になっており、その曲率が独特の魅力を醸し出している。
最後に、フェロシアン化金属化合物が福島原発事故の放射線物質であるセシウムからの放射線を吸収する記載があるのも見逃せない。
鉄がこの様に広範囲な用途を持つ事を紹介する本書の価値は非常に大きいと言える。
鉄についての発生から役割などをあらゆることに廣く深く難しい計算がなく、解説されています。小学生でもわかる内容です。繰り返し読んでいますが、鉄が地球に対して行った作用や、製鉄技術・利用方法等鉄を科学的に説明されて居ます。
【概要】
(分野)素材、雑学
(頁数)前書&目次8頁 + 本文180頁 + 索引2頁
(出版日)2016/2/16
本書は、「元素」「物性」「地質」「合金」「製造業」「歴史」「伝統工芸」「生体」という切り口から、一番身近な金属である「鉄」を幅広く説明していますが、「鉄」に限らず金属全般についての説明も同様になされています。
【内容】
「元素」や「物性」の部分では、鉄と、金やニッケルなど、他の金属との比較から、鉄の「重く、溶けにくく、錆びやすい」性質を化学的に説明しています。
こうした化学を用いた金属間での特徴づけは、後に「鉄」をベースにした「合金」の話題の中で、「なぜ鉄に銅や、ニッケル、スズなどの金属を混ぜるのか?」という疑問に明快な答えを与えてくれています。
また、「歴史」や「伝統工芸」の部分では、製鉄技術から日本刀の製造に至るまでの、世界や日本での製鉄の歴史が概説されています。ジブリ映画「もののけ姫」で出てきた「たたら製鉄」が、実は日本独自で発展した製鉄技術であること、更には、日本刀の浮かび上がる「刃紋」についても説明されており興味深いです。
【感想】
単なる「鉄」の話題に収まらず、金属に関する幅広い知見を得ることが出来ます。「合金」や「歴史」の部分は、特に詳しく書かれており、「鉄」という金属の親近感を改めて感じました。
他の方のレビューに細かく書かれてあるので、割愛させていただきますが、
大変勉強になる本でした。
ダマスカスブレードが実はインドの技術だったとは、知りませんでした。
単純に鉄だけのお話しではないのも、気に入りました。
中身の情報量がほとんどなくペラペラ。
書籍としてまとめるならもっと深堀が必要ではないかと
価格ほどの価値はない本です
