増補改訂版 地層の見方がわかるフィールド図鑑: 岩石・地層・地形から地球の成り立ちや活動を知る解説
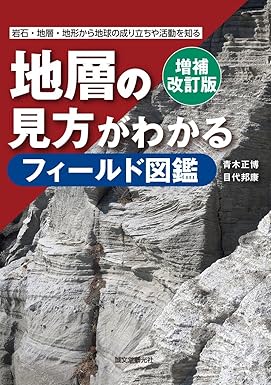
増補改訂版 地層の見方がわかるフィールド図鑑: 岩石・地層・地形から地球の成り立ちや活動を知る口コミ
初期の学習には最適です。
僕みたいな素人の者でも分かりやすく!尚且つカラー写真でより理解出来る本でした。
地質学的な観点からトピックを取り上げ(例:地滑り、氷河地形、カルデラ、海底溶岩と瑪瑙、花崗岩、熱水金鉱床・・・)、地学的な解説を加え、代表的な場所の写真を添えてあります。
解説も明快で分かりやすいのですが、何よりも写真のインパクトが凄い。
一見して、大地の驚異を実感出来、是非とも見に行きたい、という気持ちにさせられます。
更に岩石肉眼鑑定の手引き、ジオパークなどについても解説され、実際に野外観察に出掛ける時の方法も紹介されています。
本書を見ると、日本が、世界でも稀に見る地質学の一大天国であることが実感出来ます。
柱状節理やカルデラなど、ある程度の地層について知っている人にはちょうどよいレベルかと思います。鈴鹿の御池岳などで登山をするとカレンフェルトやドリーネに出くわしますが、その他、本書を読んで、結晶片岩、ホルンフェルス、枕状溶岩(マグマがゆっくり流れながら固まったもの)、岩脈(マグマが隙間を通って凝固した部分の侵食残存部)のように、山で見かける地層についての知識がつきました。
また、全国色々な温泉に行きましたが、源泉掛け流しの露天風呂に行くと、火山性の硫黄の温泉以外に、本書で取り上げられている中性の石灰を主とする温泉沈殿物の珪華や時には藍藻などが白くコーティングされた網の目のようなちょっと気持ち悪いものも見かけます。
あと、成り立ちについて意外に知らなかったのが、水中の植物遺骸が泥炭となり、泥炭に圧力がかかったものが石炭だったり、平面な磯と切り立った崖は隆起した台地の裾が海食崖という波で侵食されたせいで出来た地形だったということ。
東京では4m50cmも地盤沈下したところがあるというのは驚きでしたが、地盤沈下は地下水の過剰な汲み上げ以外に、砂防ダムで川から土砂が運ばれなくなったことが原因であるというのは初めて知りました。河川の氾濫をおさえて安心していたら副作用があるのですね。
最後に著者が、地層用語のそれぞれに一言を配しているのが面白いです。例えば、マグマの上昇流に乗って運ばれた異質な鉱物のことをゼノリスと言いますが、それを一言として、「茶碗蒸しの銀杏のごとし」。玉子と異質な銀杏が蒸されているうちに玉子の中に混じって固定されているのが良い例えで覚えやすいです。
地層に興味がある初心者向け
『ブラタモリ』の影響というわけでもないでしょうが、近ごろ、地層に興味を持つ方が増えていると聞きました。ジオパークを訪れたり、地層を見にハイキングに出かけたり。ぼくも地層や岩石がすごく好きなので、いろんな本を読みながらフィールドワークに行きたいなあと考えています。
この本はとてもいい本だと思います。
まず大きくてわかりやすい写真がたくさん載っています。現地に行かなくてもよくわかる、いい写真がいっぱいです。
ただし、説明文はちょっととっつきにくいです。文章自体はわかりやすいのですが、話の流れがごちゃごちゃしていて、「え、そこから始めるんですか?」「なんの話でしたっけ…」と、すんなり頭に入ってこないことがあります。字は大きいので、年配の方にも読みやすい(写真のキャプションの字は小さめ)。難しい用語も出てくるが、基本的にルビは振っていない。
50くらいのテーマでいろいろ解説しています。たとえばこんな内容。
・地層とは何か?
・地すべり、崩壊
・花崗岩
・ホルンフェルス
・柱状節理
・火山の断面
・タフォニ
・平野の川
・湧き水
あまり体系だった構成にはなっていないので、興味のあるところから読んでいけばいいと思います。
最後に20ページくらい、「野外観察の基礎知識」として、フィールドワークの進め方や注意点が書かれているので実用的です。この項目以外はすべてカラーです。
地層(露頭?)をタイプ別に、46項目に分けて写真付きで紹介しています。
以前、図書館で改定前の図鑑を見て内容が解りやすく気に入り、amazonで注文検索をしたところ廃版との事で諦めました。
その後、数ヶ月後に増補改訂版の案内メールが届き即買いしました。大変嬉しく満足してます。
