金属疲労の基礎と疲労強度設計への応用解説
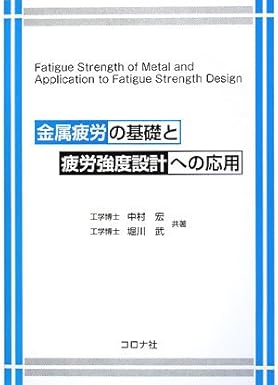
金属疲労の基礎と疲労強度設計への応用口コミ
疲労のことを詳しく漏れなくコンパクトに述べてくれている。実用性が高いと思います。
振動を受ける部品を固定するためのマウント、ステー、ブラケットの強度検討の際、限度線図の考え方や圧縮側の平均応力の考え方、SN線図への平均応力の考慮、安全率の取り方など、ちゃんとした根拠を理解せずに伝え聞いた情報でそれらを考慮しているという状況でした。この本でそのような「あやふや」が一気に解決できました。もちろん今まで知らなかったことも多く記載されていたため、得られた新たな知識を今後の実務に取り入れていきたいと思います。
設計技術者に適したオーソドックスな疲労テキストを書店で探すと、他に選択肢が少ないため本書を買うことになる(私もその一人)。後半の100頁が著者らの経験(多くは70年代までの試験評価結果)であり、疲労メカニズムや耐疲労設計に関する説明は幅広いテーマにもかかわらず前半の130頁のみ。概説が多く初学者には不親切かもしれない。モードⅠ型など「き裂面の変位モード」、低温環境で重要な「延性-脆性遷移」、き裂進展解析で重要な「き裂開閉口挙動」など、殆ど説明なしである。有名なマイナー則に関し「航空機機体に使われるアルミ合金の実験などで疲労寿命をある程度説明できるため実機の疲労寿命推定に利用されている」とあるが、私の知る限り航空機開発の現場では使われない。2008年の刊行であるが、内容の古さ(引用文献は殆どが80年代まで)は否定できず、改訂の必要性が感じられる。なお、以下の様な誤記には要注意。「鉄鋼など金属材料の結晶粒の大きさは数μm(p21,22)」(正しくは数十μm)、「ゲルバー式は修正グッドマン式より安全側(p55)」(非安全側)、「平滑材の疲労限度をαで割った値を縦軸の切片に(p58)」(βで割った値)。これら以外にも小さな間違いが散見されるので、注意されたし。
大学で買わされそうな地味な装丁だが、内容は良かった。
理解できればかなり設計のレベルアップができそうです。
おすすめ。
